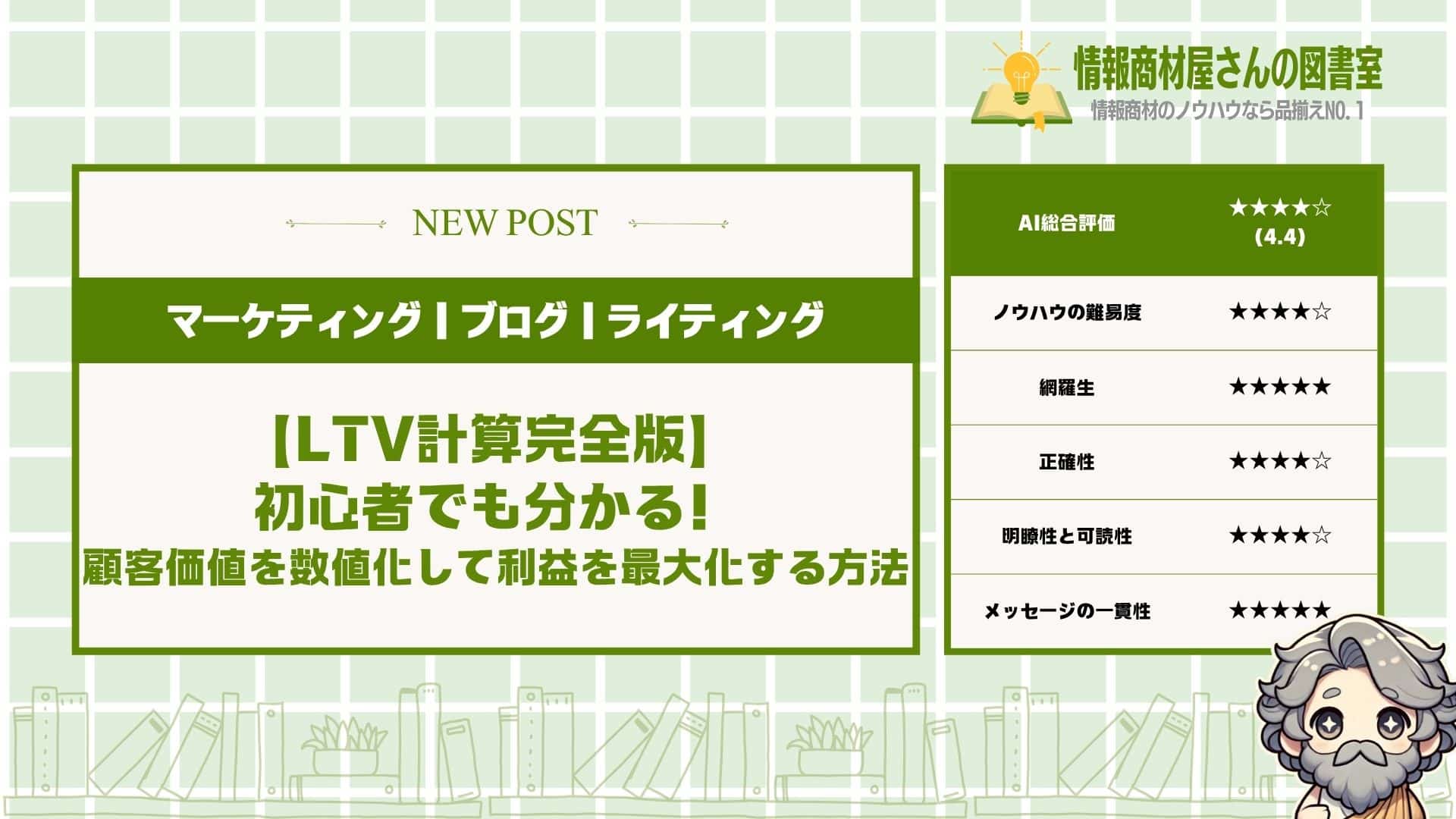このノウハウについて
AI総合評価|★★★★☆(4.4)
| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |
| 網羅生 | ★★★★★ |
| 正確性 | ★★★★☆ |
| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |
| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |
総評
ビジネスの数字を使った分析方法が体系的に学べます。仮説検証からLTV計算、リピート率向上まで、売上アップに直結する実践的なテクニックが満載です。データ分析が苦手な方でも、具体的なステップに沿って進めることで、確実に利益向上を実現できる内容となっています。
情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。
動画や音声でも記事をご覧になれます↓
はじめに
●売上が伸び悩んでて、何を改善すればいいか分からない
●数字での分析って難しそうで、どこから手をつけていいか迷ってる
●感覚じゃなくて、ちゃんとしたデータで判断できるようになりたい
ビジネスを成長させたいと思っても、
「何をどう改善すればいいのか」が
見えずに悩んでいる人は非常に多いです。
そこでこの記事では、
数字が苦手な人でも確実に実践できる
『仮説検証分析の基本』から
『利益を最大化する具体的な方法』まで
すべて解説します。
この記事を読めば
「データを使って売上を伸ばす
本当に必要な手順と考え方」が
すべて分かります。
10年以上のビジネス経験で培った
分析ノウハウと改善テクニックを凝縮しました。
本気で利益を上げたい人は最後まで読んでください。
この記事で学べること
この記事で学べる内容
- 仮説検証分析で売上を劇的に改善する4つの理由
- データ分析を成功させる5つのステップ
- LTVを正確に計算して投資判断の精度を上げる方法
- リピート率を効果的に計測する3つの実践法
- 見込み利益を最大化する5つの戦略
- 数値計測で失敗しない4つの注意点
- 利益向上につながる実践テクニック6選
仮説検証分析が重要な4つの理由
仮説検証分析って言葉を聞くと、
なんか難しそうって思うかもですが、
実はビジネスを成功させる
一番の近道なんです。
これをマスターしちゃえば、
勘に頼らずに確実に売上を伸ばせるし、
無駄な時間やお金を使わなくて済みます。
その理由がこの4つ。
- ビジネス改善を数値で判断できるから
- 顧客の評価を客観的に管理できるから
- 成約率の向上につながるから
- 効果的な施策を打てるから
どれも聞いたことがあるかもですが、
実際にできてる人って意外と少ない。
特に数字で管理するって部分が
みんな苦手なんですよね。
でも、この4つを理解して実践すれば、
あなたのビジネスは劇的に変わります。
それぞれ解説していきます。
ビジネス改善を数値で判断できるから
ビジネス改善を数値で判断できるのが、
仮説検証分析の一番のメリットなんです。
なぜかって言うと、
数字があれば感情に左右されずに
正しい判断ができるからですね。
例えば、
- 今月の売上が先月より10%アップした
- アクセス数は増えたけど成約率が下がった
- 広告費を2倍にしたら問い合わせが3倍になった
こんな風に数字で見ると、
何が良くて何がダメなのか
一目瞭然じゃないですか。
もっと具体的に言うと、
「なんとなく調子が良い気がする」
じゃなくて、
「成約率が3%から5%に上がった」
って分かるんです。
これって本当に大切で、
数字がないと改善のしようがない。
だって、何をどう改善すればいいか
分からないじゃないですか。
でも数字があれば、
「ここを改善すれば売上が上がる」
って明確に分かるんですよね。
だからこそ、
数値での判断が欠かせないんです。
顧客の評価を客観的に管理できるから
顧客の評価を客観的に管理できるのも、
めちゃくちゃ重要なポイントなんですよ。
その理由は、
自分の思い込みを排除して
本当の顧客の声が聞けるからです。
具体的には、
- アンケートの満足度スコア
- リピート購入率
- 口コミやレビューの評価
こういったデータを
しっかり数字で管理するんです。
例えばですが、
「お客さんは喜んでくれてる」
って思ってても、
実際にアンケートを取ってみたら
満足度が60%しかなかった、
なんてことがよくあるんです。
逆に、
「ちょっと心配だな」
って思ってた商品が、
実はお客さんからの評価が
めちゃくちゃ高かったりする。
これって感情で判断してたら
絶対に気づけないことですよね。
でも数字で管理してれば、
お客さんの本音が見えてくる。
そうすると、
どこを改善すればもっと喜んでもらえるか
はっきり分かるんです。
だから客観的な管理が
すごく大切なんですよね。
成約率の向上につながるから
成約率の向上につながるのが、
仮説検証分析の醍醐味ですね。
これができるようになると、
同じアクセス数でも売上が
2倍、3倍になることもあります。
なぜそんなことが可能かって言うと、
- どこで離脱してるかが分かる
- どの部分で迷ってるかが見える
- 成約に至るまでの流れが把握できる
こんな風に、
お客さんの行動パターンが
手に取るように分かるからです。
例えば、
商品ページを見た人が100人いて、
そのうち購入したのが3人だったとします。
これだと成約率は3%ですよね。
でも分析してみると、
「価格の部分で70%の人が離脱してる」
って分かったとしましょう。
そしたら価格の見せ方を変えたり、
分割払いを導入したりして
改善できるじゃないですか。
実際に僕の知り合いも、
決済ページの文言を少し変えただけで
成約率が2%から5%に上がったって
言ってましたからね。
こういう改善を積み重ねることで、
売上がどんどん伸びていくんです。
だからこそ、
成約率の向上は欠かせません。
効果的な施策を打てるから
効果的な施策を打てるようになるのが、
仮説検証分析の最終ゴールなんです。
なぜ効果的な施策が打てるかって言うと、
データに基づいて戦略を立てられるから。
つまり、
- 何をすれば効果があるかが分かる
- 無駄な施策に時間を使わなくて済む
- 予算を効率的に使える
こんなメリットがあるんですよね。
例えばですが、
広告を出すときも、
「とりあえずFacebook広告やってみよう」
じゃなくて、
「30代女性からの反応が良いから
Instagram広告に集中しよう」
って判断できるんです。
もっと言うと、
過去のデータを見て、
「この時期にこの商品を売ると
いつもより20%売上が上がる」
みたいなことも分かってくる。
実際に、
あるECサイトの運営者は、
データ分析をしっかりやるようになってから
広告費を半分に減らしたのに
売上が1.5倍になったって話もあります。
これって本当にすごいことで、
同じ努力でも結果が全然違ってくる。
だからこそ、
効果的な施策を打つために
仮説検証分析が必要なんです。
仮説検証分析を実践する5つのステップ
ビジネスで結果を出したいなら、
感覚じゃなくて数字で判断すること。
これができるようになると、
売上アップの具体的な道筋が見えてきます。
その方法が、
- STEP1. 現状のデータを収集する
- STEP2. 改善すべきポイントを特定する
- STEP3. 具体的な改善仮説を立てる
- STEP4. 施策を実行する
- STEP5. 結果を数値で検証する
この5つなんですよね。
多くの人が「なんとなく」で
ビジネスを進めちゃってるんです。
でも数字を使って分析すれば、
どこを改善すれば良いかが丸わかり。
順番に解説していきます。
STEP1. 現状のデータを収集する
現状のデータ収集っていうのは、
今のビジネスの状況を数字で把握すること。
これをやらないと、
何を改善すべきかが分からないんです。
具体的には、
- アクセス数
- 成約率
- 購買プロセスの各段階での離脱率
こういうデータを集めるんですね。
例えばですが、
月間1000人がサイトに来てて、
そのうち10人が商品を買ってくれてるとします。
そうすると成約率は1%ですよね。
この1%っていう数字が分かれば、
「成約率を2%に上げれば売上が2倍になる」
って具体的な目標が立てられるんです。
逆にこの数字を知らないと、
「もっと頑張ろう」みたいな
ふわっとした改善しかできません。
だからこそ、
まずは現状を数字で把握することが超重要。
STEP2. 改善すべきポイントを特定する
改善すべきポイントの特定は、
集めたデータの中から一番効果的な部分を見つけること。
なぜなら、全部を一気に改善するより、
一つずつ集中した方が結果が出やすいからです。
見るべきポイントは、
- 離脱率が高い箇所
- 成約率が低い部分
- アクセス数が少ない原因
この辺りですね。
さっきの例で言うと、
1000人のアクセスがあって10人しか買わない場合、
990人が離脱してるってことじゃないですか。
この990人がどこで離脱してるかを調べるんです。
商品ページを見た瞬間に帰っちゃうのか、
それとも価格を見て諦めちゃうのか。
こういう細かい部分を数字で追っていくと、
「ここを直せば一番効果が出そう」
っていうポイントが見えてきます。
そのポイントが特定できたら、
そこに集中して改善していけばいいんです。
STEP3. 具体的な改善仮説を立てる
具体的な改善仮説を立てるっていうのは、
「こうすれば数字が良くなるはず」っていう予想を作ること。
この仮説があることで、
施策の方向性がブレなくなるんですよね。
仮説の立て方としては、
- 商品ページの見出しを変える
- 価格の見せ方を工夫する
- お客様の声を追加する
こんな感じで具体的にするんです。
例えば、商品ページで90%の人が離脱してるなら、
「見出しが魅力的じゃないから興味を持ってもらえない」
っていう仮説が立てられますよね。
そしたら、
「見出しをもっと具体的なベネフィットに変えれば、
離脱率が下がって成約率が上がるはず」
っていう仮説になるんです。
大切なのは、
「なんとなく良くなりそう」じゃなくて、
「こういう理由でこの数字が改善されるはず」
って論理的に考えること。
そうすることで、
施策の効果を正しく測定できるようになります。
STEP4. 施策を実行する
施策を実行するときは、
立てた仮説に基づいて一つずつ試していくこと。
複数の変更を同時にやっちゃうと、
どれが効果があったのか分からなくなっちゃうんです。
実行するときのポイントは、
- 一度に一つの変更だけ行う
- 変更前のデータを必ず記録しておく
- 十分なデータが集まるまで待つ
この3つですね。
さっきの見出し変更の例だと、
まずは見出しだけを変えて、
他の部分は一切触らないんです。
そして変更前は成約率1%だったのを記録しておいて、
変更後に1週間とか2週間データを取る。
この期間中に「やっぱりボタンの色も変えよう」
とか思っても我慢するんです。
なぜかっていうと、
見出しの効果なのかボタンの色の効果なのか
分からなくなっちゃうから。
地味な作業だけど、
この我慢ができるかどうかで結果が全然変わってきます。
STEP5. 結果を数値で検証する
結果を数値で検証するっていうのは、
施策の効果を客観的に判断すること。
感覚じゃなくて数字で判断するから、
次にやるべきことが明確になるんです。
検証で見るべき数字は、
- 改善前後の成約率の変化
- アクセス数の変化
- 売上の変化
こういった具体的な数値ですね。
例えば見出しを変えた結果、
成約率が1%から1.5%に上がったとします。
そうすると「仮説が正しかった」って分かるし、
さらに改善を続ければもっと良くなる可能性が高い。
逆に成約率が0.8%に下がっちゃったら、
「この方向性は間違ってた」って判断できる。
そしたら元に戻して、
別の仮説を試せばいいんです。
この検証作業をやることで、
「何が効果があって何が効果ないか」
っていうノウハウが蓄積されていきます。
そのノウハウがあるからこそ、
次の施策がもっと的確になるし、
ビジネス全体がどんどん改善されていくんですよね。
仮説検証分析を成功させる実践テクニック3つ
仮説検証分析って、
実は3つのテクニックを
押さえるだけで劇的に変わるんです。
これを知ってるか知らないかで、
あなたのビジネス改善スピードが
10倍変わってきます。
その3つのテクニックが、
- 仮説設定シートを活用する
- 定期的な振り返り会議を実施する
- 改善サイクルを継続的に回す
なんですよね。
多くの人が数字を見るのが苦手で、
なんとなく感覚で判断しちゃう。
でも、この3つを使えば
数字が苦手な人でも
ちゃんと結果が出せるんです。
順番に詳しく
見ていきましょう。
仮説設定シートを活用する
仮説設定シートっていうのは、
あなたの予想を整理するための
魔法のツールなんです。
これがあるからこそ、
後から「なんで上手くいかなかったんだろう」
って迷子にならずに済むんですよね。
具体的には、
- 何を改善したいのか
- どんな結果を期待してるのか
- いつまでに達成したいのか
こんなことを書き出すんです。
例えばですけど、
「ホームページの問い合わせを増やしたい」
って思ったとしますよね。
その時に、
「お問い合わせボタンを大きくしたら、
月の問い合わせが10件から15件に増える」
みたいに具体的に書くんです。
さらに詳しく言うと、
「なぜボタンを大きくすると増えるのか」
の理由も一緒に書いておく。
「今のボタンが小さくて気づかれてないから」
とか、そういう根拠も
セットで記録しておくんです。
こうやって最初に予想を
きちんと書いておくことで、
後から検証がめちゃくちゃ楽になる。
だからこそ、
仮説設定シートは絶対に使いましょう。
定期的な振り返り会議を実施する
振り返り会議っていうのは、
要するに「答え合わせの時間」を
ちゃんと作るってことです。
これをやらない人が本当に多くて、
せっかく良い施策をやっても
結果を見ずに終わっちゃうんですよね。
振り返り会議でやることは、
- 予想通りだった部分はどこか
- 予想と違った部分はどこか
- 次に何を試すべきか
この3つを確認するんです。
たとえばさっきの例で言うと、
「ボタンを大きくしたら
本当に問い合わせが増えたのか」
を数字で確認するわけです。
もし15件に増えてなくて
12件だったとしたら、
「なぜ3件足りなかったのか」
を考えるんですよね。
実際に僕の知り合いの会社では、
毎週金曜日の夕方に
30分だけ振り返り会議をやってます。
そしたら、
「思ってたより効果が薄かった施策」
とか「予想以上に効果があった施策」
がはっきり分かるようになったんです。
振り返りをしないと、
何が良くて何が悪いのか
永遠に分からないまま。
だから定期的な振り返り会議は
絶対に欠かせないんです。
改善サイクルを継続的に回す
改善サイクルっていうのは、
「やってみる→確認する→直す」
を何度も繰り返すことですね。
一回やって終わりじゃなくて、
ずーっと続けることが
めちゃくちゃ大事なんです。
改善サイクルの流れは、
- 仮説を立てる
- 実際にやってみる
- 結果を数字で確認する
- 次の改善案を考える
この4つをぐるぐる回すんです。
例えば、先ほどのボタンの話で言うと、
大きくしても効果が薄かったら
今度は「色を変えてみよう」
とか「位置を変えてみよう」
って次の手を打つんですよね。
僕が知ってるネットショップでは、
毎月1つずつ改善を試してて、
1年間で売上が2倍になったんです。
最初は商品写真を変えて、
次は商品説明文を変えて、
その次は送料の表示方法を変えて...
みたいに、
小さな改善を積み重ねていった。
一つ一つは小さな変化でも、
続けることで大きな結果に
つながるんですよね。
逆に、一回だけやって
「効果がなかった」って諦めちゃうと、
そこで成長が止まっちゃう。
だからこそ、改善サイクルを
継続的に回し続けることが
成功の秘訣なんです。
数字を正しく理解して活用する3つの方法
数字って見ただけで
頭が痛くなっちゃう人多いですよね。
でもね、数字を正しく理解できるようになると、
ビジネスがガンガン改善できるようになるんです。
その具体的な方法が、
- データの背景と意味を深く読み取る
- 複数の指標を組み合わせて判断する
- 継続的にデータを追跡して変化を捉える
この3つなんですよね。
数字が苦手な人でも、
何度も見直していけば絶対に理解できます。
数字を使った管理ができるようになれば、
具体的な改善策がどんどん見えてくるんです。
それぞれ解説していきます。
データの背景と意味を深く読み取る
データの背景と意味を読み取るっていうのは、
数字の裏側にある「なぜ」を理解することなんです。
数字だけ見てても、
本当の問題は見えてこないからですね。
例えば、こんなことがあります。
- 売上が下がった理由
- アクセス数が増えた背景
- お客さんの行動パターンの変化
これらを深く掘り下げることが大切です。
たとえばですが、
「今月の売上が先月より20%下がった」
っていう数字があったとしますよね。
でも、その背景を調べてみたら、
実は競合他社がキャンペーンをやってて、
お客さんがそっちに流れてただけだった。
そうすると対策も変わってきますよね。
単純に「売上を上げよう」じゃなくて、
「競合に負けないキャンペーンを打とう」
っていう具体的な改善策が見えてくるんです。
だからこそ、数字の背景を
しっかり読み取ることが重要なんですよね。
複数の指標を組み合わせて判断する
複数の指標を組み合わせるっていうのは、
1つの数字だけで判断しないってことですね。
1つの数字だけ見てると、
間違った判断をしちゃうことが多いんです。
具体的には、
- 売上と利益率を一緒に見る
- アクセス数と滞在時間を組み合わせる
- 新規客数とリピート率を同時にチェック
こんな感じで複数見るんです。
例えばね、
「今月はアクセス数が過去最高だった!」
って喜んでたとしますよね。
でも滞在時間を見てみたら、
実は平均10秒しかサイトにいなかった。
これだと全然意味ないじゃないですか。
アクセス数は多いけど、
お客さんはすぐに帰っちゃってる。
そうすると改善策も変わってきます。
「アクセス数を増やそう」じゃなくて、
「サイトの内容を改善して滞在時間を延ばそう」
っていう方向になるんです。
こうやって複数の指標を見ることで、
本当に必要な改善策が見えてくるんですよね。
継続的にデータを追跡して変化を捉える
継続的にデータを追跡するっていうのは、
一回だけじゃなくて定期的に数字をチェックすることです。
変化を捉えることで、
施策の効果がちゃんと検証できるんですよね。
たとえば、
- 毎週同じ曜日にデータをチェック
- 月末に必ず数字をまとめる
- 改善策を実行した前後で比較する
こういう習慣が大切なんです。
実際に僕の知り合いの会社では、
毎週月曜日に必ず数字の確認会議をやってるんです。
そうすると、
「先週のキャンペーンの効果はどうだった?」
「今週はどこを改善しよう?」
っていう話ができるんですよね。
継続的に見てるからこそ、
小さな変化にもすぐ気づけるんです。
例えば、
「なんか今週は問い合わせが少ないな」
って早めに気づいて対策できる。
一回だけ見てたら、
「今月は調子悪かったな」
で終わっちゃうじゃないですか。
でも継続的に見てれば、
どのタイミングで何が起きたかが分かるんです。
だからこそ、継続的なデータ追跡が
ビジネス成長には欠かせないんですよね。
仮説検証分析で失敗しないための注意点4つ
仮説検証分析で失敗する人って、
実は同じようなミスを繰り返してるんです。
この4つのポイントを押さえとけば、
数字を使った改善がスムーズに進みます。
その4つが、
- データの精度を確保すること
- 短期間で結果を求めすぎないこと
- 複数の指標を同時に見ること
- 継続的に改善サイクルを回すこと
なんですよね。
どれも当たり前に見えるかもですが、
実際にできてる人は意外と少ない。
この4つを意識するだけで、
仮説検証の成功率がグッと上がるんです。
それぞれ解説していきます。
データの精度を確保すること
データの精度を確保するっていうのは、
正しい数字を集めることです。
間違った数字で分析しても、
間違った結論しか出てこないからですね。
例えば、
- アクセス数の重複カウント
- 成約率の計算ミス
- サンプル数が少なすぎる
こんなミスがよくあります。
もっと具体的に言うと、
100人のお客さんのうち5人が買ったとき、
成約率は5%ですよね。
でも、もしアクセス数を
間違って200人でカウントしてたら、
成約率は2.5%になっちゃいます。
これだと全然違う結論になるし、
改善策も的外れになっちゃうんです。
だからこそ、まずは正確な数字を
集めることから始めましょう。
計測ツールの設定を見直したり、
データの取り方をチェックしたり。
地味な作業だけど、
これが一番大切なんです。
短期間で結果を求めすぎないこと
短期間で結果を求めすぎちゃダメです。
なぜかっていうと、
仮説検証って時間がかかるものだから。
特に、
- データが溜まるまでの時間
- お客さんの行動パターンの変化
- 季節要因の影響
これらを考慮する必要があります。
例えばね、
新しい広告を出して1週間で
「効果がない」って判断しちゃう人がいるんです。
でも実際は、お客さんが商品を知ってから
買うまでに1ヶ月かかることもあるじゃないですか。
だから1週間じゃ全然分からないんですよね。
最低でも1ヶ月、
できれば3ヶ月は様子を見た方がいいです。
そうしないと、
本当は効果があるのに途中でやめちゃったり、
逆に効果がないのに続けちゃったりします。
焦る気持ちは分かるけど、
じっくり腰を据えて取り組みましょう。
複数の指標を同時に見ること
複数の指標を同時に見るのが大切です。
1つの数字だけ見てても、
全体像が分からないからなんです。
チェックすべき指標は、
- アクセス数
- 成約率
- 客単価
- リピート率
こんな感じですね。
例えば、成約率だけ見て
「今月は調子いいな」って思ってても、
実はアクセス数が半分になってたりするんです。
そうすると売上は変わらないか、
むしろ下がってる可能性もありますよね。
逆に、成約率が下がっても
アクセス数が倍になってれば、
売上は上がってるかもしれません。
だから、いろんな角度から
数字を見る必要があるんです。
まるで健康診断みたいなもので、
血圧だけじゃなくて血糖値も体重も
全部チェックするじゃないですか。
ビジネスも同じで、
総合的に判断することが大切なんです。
継続的に改善サイクルを回すこと
継続的に改善サイクルを回すことです。
一回やって終わりじゃなくて、
ずっと続けていくことが重要なんですね。
改善サイクルっていうのは、
- 現状分析
- 仮説立て
- 施策実行
- 結果検証
この流れを繰り返すことです。
例えば、ホームページの成約率を
上げたいとしますよね。
最初は「ボタンの色を変えてみよう」
って仮説を立てて実行します。
結果を見て効果があったら、
次は「文章を変えてみよう」
って新しい仮説を立てるんです。
こうやって少しずつ改善していくと、
最初は1%だった成約率が
気がついたら3%になってたりします。
でも、多くの人は一回やって
「あまり変わらなかった」
って諦めちゃうんですよね。
実際は、小さな改善の積み重ねが
大きな結果につながるんです。
だからこそ、継続して
改善サイクルを回し続けましょう。
LTV(顧客生涯価値)を計測すべき3つの理由
LTVを計測することで、
あなたのビジネスが劇的に変わります。
この数字を知ることで、
どの商品に力を入れるべきか、
どこにお金をかけるべきかが
手に取るように分かるんです。
計測すべき理由は、
- 商品の真の収益性が把握できるから
- 投資判断の精度が向上するから
- 長期的な事業戦略が立てられるから
この3つなんですよね。
多くの人がLTVを
なんとなくでしか見てないんですが、
実はめちゃくちゃ重要な指標なんです。
この3つを理解すれば、
あなたのビジネスの見え方が
ガラッと変わりますよ。
それぞれ解説していきます。
商品の真の収益性が把握できるから
商品の本当の価値っていうのは、
LTVを見ないと絶対に分からないんです。
なぜかって言うと、
売上だけ見てても
その商品がどれだけ稼いでくれるかは
見えてこないからなんですよね。
例えば、
- 単発で3万円の商品
- 月額5千円のサブスク商品
- リピート率80%の1万円商品
こんな感じで商品があったとします。
一見すると3万円の商品が
一番良さそうに見えるじゃないですか。
でも実際は、
月額5千円のサブスクが
平均12ヶ月続くとしたら
LTVは6万円になるんです。
リピート率80%の商品だって、
平均3回買ってもらえるなら
LTVは3万円になります。
ここで大切なのが、
売り切り商品とサブスクリプション商品では
計算方法が全然違うってことなんです。
サブスクなら月額料金×継続月数、
売り切りなら単価×リピート回数で
計算していく感じですね。
このLTVがシステム全体の
見込み利益を考える時の
超重要な指標になってくるんですよ。
投資判断の精度が向上するから
投資判断の精度が上がるっていうのは、
どこにお金をかけるべきかが
めちゃくちゃ明確になるってことなんです。
これが分かると、
広告費とか人件費とかの
投資配分で迷わなくなります。
具体的には、
- LTVが高い商品への広告投資
- 収益性の低い商品の改善投資
- 新規顧客獲得コストの上限設定
こういった判断が
スパッとできるようになるんです。
例えばですけど、
LTVが10万円の商品があるとしたら、
新規顧客獲得に3万円かけても
まだ7万円の利益が残るじゃないですか。
でもLTVが2万円の商品だったら、
3万円かけちゃったら赤字になっちゃう。
こんな風に、
LTVを知ってるかどうかで
投資判断の質が全然変わってくるんです。
さらに言うと、
各商品の見込み利益を
合算することで、
システム全体の見込み利益も
算出できるようになります。
これができれば、
会社全体の投資戦略も
立てやすくなるんですよね。
長期的な事業戦略が立てられるから
長期的な事業戦略が立てられるっていうのは、
将来の収益予測ができるようになるってことです。
これができると、
今やってることが正しいのか、
どこを改善すべきなのかが
はっきり見えてくるんですよね。
例えば、
- 3年後の売上予測
- 顧客数の増加計画
- 新商品開発の優先順位
こういったことが
データに基づいて決められます。
特に重要なのが
リピート率の計測なんです。
リピート率っていうのは、
顧客が再度商品を購入する割合のこと。
月間リピート顧客数を
累計新規顧客数で割って
算出していくんですが、
これがめちゃくちゃ大事なんですよ。
リピーターっていうのは、
2回以上商品を購入した顧客のことで、
この人たちがいるかどうかで
ビジネスの安定性が全然違ってきます。
見込み利益の計算も
将来的な収益の予測に
めちゃくちゃ役立つんです。
商品のLTVと購入者数を使って
見込み利益を計算して、
それを積み重ねていくことで
長期的な戦略が立てられるんですよね。
商品ごとのLTVを正確に計算する4つのステップ
商品ごとのLTVを正確に計算すれば、
どの商品が本当に稼げるかが丸わかりになります。
これができるようになると、
無駄な商品に時間をかけることがなくなって、
利益の出る商品だけに集中できるんです。
LTV計算の4つのステップは、
- STEP1. 商品タイプを分類する
- STEP2. 平均購入単価を算出する
- STEP3. 購入頻度を計測する
- STEP4. 顧客維持期間を設定する
この順番でやっていけば、
どんな商品でもLTVが計算できます。
売り切り商品とサブスク商品では
計算方法が全然違うから、
まずは商品タイプの分類が超重要なんですよね。
それぞれ解説していきます。
STEP1. 商品タイプを分類する
商品タイプの分類っていうのは、
あなたの商品が売り切りかサブスクかを
はっきりさせることです。
なぜかというと、
この2つではLTVの計算方法が
まったく違うからなんですよね。
例えば、
- 売り切り商品(本、コース、セミナー)
- サブスク商品(月額サービス、定期購入)
こんな感じで分けられます。
売り切り商品の場合は、
お客さんが一回買ったらそれで終わり。
でも実際には、
同じお客さんが別の商品を買ったり、
同じ商品をもう一回買ったりすることもありますよね。
一方でサブスク商品は、
毎月継続的にお金が入ってくる。
だから計算するときに、
「何ヶ月続けてくれるか」
っていう要素が必要になるんです。
この違いを理解しないと、
LTVの計算が全然違う数字になっちゃいます。
だからこそ、
まずは商品タイプをしっかり分類しましょう。
STEP2. 平均購入単価を算出する
平均購入単価っていうのは、
お客さん一人あたりが一回の購入で
いくら使ってくれるかの平均値です。
これが分からないと、
LTVの計算ができないんですよね。
計算方法は、
- 総売上 ÷ 購入回数 = 平均購入単価
こんな感じでシンプルです。
例えば、
10万円の売上があって、
20回購入されたとしたら、
平均購入単価は5,000円になります。
ここで注意したいのが、
商品によって単価がバラバラな場合です。
3,000円の商品と10,000円の商品を
両方売ってる場合、
どっちがよく売れるかで平均が変わってきます。
だから最低でも3ヶ月分のデータを使って、
正確な平均を出すのがおすすめですね。
データが少ないと、
たまたま高い商品が売れた月だけ見て
「平均単価が高い!」
って勘違いしちゃうことがあるんです。
正確な平均購入単価を出せれば、
LTV計算の精度がグッと上がります。
STEP3. 購入頻度を計測する
購入頻度を計測するっていうのは、
お客さんが一定期間にどれくらいの回数
商品を買ってくれるかを調べることです。
これを知ることで、
一人のお客さんからどれくらいの売上が
期待できるかが見えてくるんです。
測定する項目は、
- 月間購入回数
- 年間購入回数
- リピート購入の間隔
こういったデータですね。
例えば、
あるお客さんが3ヶ月で2回購入したら、
月間購入頻度は0.67回になります。
年間だと8回くらいの計算になりますよね。
でも実際には、
最初の方はよく買ってくれるけど、
だんだん購入頻度が下がることが多いんです。
だから月ごとに購入頻度を追跡して、
どんなパターンで変化するかを
把握しておくのが大切です。
サブスク商品の場合は、
継続率を見ることになります。
1ヶ月目は100%でも、
2ヶ月目は80%、3ヶ月目は60%
みたいに下がっていくのが普通ですからね。
購入頻度が正確に分かれば、
LTVの予測精度が一気に上がります。
STEP4. 顧客維持期間を設定する
顧客維持期間を設定するっていうのは、
お客さんがどれくらいの期間
あなたから商品を買い続けてくれるかを
決めることです。
これがLTV計算の最後のピースで、
一番重要な部分でもあるんですよね。
設定方法としては、
- 過去のデータから平均を算出
- 業界平均を参考にする
- 保守的な期間を設定する
こんなアプローチがあります。
例えば、
サブスク商品で平均継続期間が6ヶ月なら、
それを顧客維持期間として設定します。
売り切り商品の場合は、
最後に購入してから何ヶ月経ったら
「もう買わない客」と判断するかを決めるんです。
ここで大事なのは、
楽観的すぎる期間を設定しないこと。
「きっと1年は買い続けてくれるだろう」
って希望的観測で設定すると、
実際のLTVとかけ離れた数字になっちゃいます。
だから過去のデータがあるなら、
それをベースにして、
少し保守的な期間を設定するのがおすすめです。
顧客維持期間が正確に設定できれば、
商品ごとのLTVが正確に計算できて、
どの商品に力を入れるべきかが
はっきり見えてきます。
リピート率を効果的に計測する3つの方法
リピート率の計測には、
3つの効果的な方法があるんです。
この方法をマスターしとけば、
お客さんがどれくらい戻ってきてくれるかが手に取るように分かります。
その3つが、
- 月間リピート率を算出する
- 期間別リピート率を比較する
- 商品別リピート率を分析する
なんですよね。
それぞれ違った角度から
リピート率を見ることができるんです。
この3つを組み合わせることで、
ビジネスの改善点がクリアに見えてきます。
それぞれ解説していきます。
月間リピート率を算出する
月間リピート率っていうのは、
その月にどれくらいのお客さんが戻ってきてくれたかを表す数字。
これを計算することで、
お客さんとの関係がどれくらい良好かが分かるんです。
計算方法は、こんな感じで、
- 月間リピート顧客数 ÷ 累計新規顧客数 × 100
- リピーターは2回以上購入した人
- 毎月継続して計測する
この計算をやってみましょう。
例えばですね、
今月リピート購入してくれた人が50人いて、
これまでに獲得した新規顧客が500人だったとします。
そうすると、
50 ÷ 500 × 100 = 10%
っていう計算になるんです。
でも注意点があって、
この数字は毎月変動するものなんですよね。
季節やキャンペーンによって
大きく変わることもあります。
だからこそ、
単月だけじゃなくて継続的に見ていくことが大切。
月間リピート率を継続して計測することで、
ビジネスの健康状態が見えてくるんです。
期間別リピート率を比較する
期間別の比較っていうのは、
異なる期間のリピート率を並べて見ること。
これをやることで、
ビジネスの成長や問題点がはっきりと見えてきます。
比較すべき期間は、
- 3ヶ月単位での比較
- 前年同月との比較
- キャンペーン前後の比較
こんな感じですね。
3ヶ月単位で見ると、
季節的な変動が見えてきます。
例えば、
夏場は10%だったリピート率が
冬場には15%に上がってるとか。
これって商品の特性や
お客さんのニーズの変化を表してるんです。
前年同月と比較すると、
ビジネスが成長してるかどうかが分かります。
去年の8月は12%だったのに
今年の8月は18%になってたら、
明らかに改善してるってことですよね。
期間別の比較をすることで、
どの施策が効果的だったかも見えてくるんです。
商品別リピート率を分析する
商品別の分析っていうのは、
それぞれの商品でリピート率がどう違うかを見ること。
これが分かると、
どの商品がお客さんに愛されてるかがバッチリ見えます。
分析すべきポイントは、
- 各商品のリピート率
- 商品ごとのLTV(顧客生涯価値)
- 売り切り商品とサブスク商品の違い
この3つなんです。
商品Aのリピート率が25%で、
商品Bのリピート率が5%だったとしましょう。
明らかに商品Aの方が
お客さんに愛されてるってことですよね。
そうすると、
商品Aのような商品をもっと作ればいいし、
商品Bは改善が必要だって分かります。
ここで大切なのが、
LTVとの関係も見ることなんです。
リピート率が高い商品は
LTVも高くなる傾向があります。
でも時々、リピート率は低いけど
単価が高くてLTVが良い商品もあるんですよね。
商品別の分析をすることで、
どの商品に力を入れるべきかが見えてくるんです。
見込み利益を最大化する5つの戦略
見込み利益を本気で伸ばしたいなら、
やみくもに売上を追いかけちゃダメなんです。
この5つの戦略をマスターすれば、
同じ労力で収益が2倍、3倍に跳ね上がります。
その戦略が、
- LTVの高い商品に集中投資する
- リピート率向上施策を実行する
- 顧客セグメント別に戦略を変える
- クロスセル・アップセルを強化する
- 顧客維持コストを最適化する
この5つなんですよね。
多くの人が売上ばかり見てるけど、
本当に大切なのは「見込み利益」です。
これって将来的にどのくらい稼げるかを
予測する超重要な数字なんです。
順番に詳しく説明していきますね。
LTVの高い商品に集中投資する
LTVが高い商品こそ、
あなたのビジネスの宝物なんです。
なぜかっていうと、
一人の顧客から長期間にわたって収益が生まれるから。
例えば、
- 月額サービスで長く使ってもらえる商品
- リピート購入される消耗品
- 追加購入が期待できる商品シリーズ
こういう商品ですね。
具体的に言うと、
1回限りの5万円商品よりも、
月額1万円で平均6ヶ月継続される商品の方がLTVは高いんです。
だって、1万円×6ヶ月で6万円になるじゃないですか。
しかも継続商品だから、
お客さんとの関係も深くなって、
さらに長期間使ってもらえる可能性も高い。
ここで注意したいのが、
売り切り商品とサブスクリプション商品では
LTVの計算方法が全然違うってこと。
売り切り商品なら商品価格がそのままLTVになるけど、
サブスクなら月額×継続月数で計算するんです。
だからこそ、自分の商品のLTVを正確に把握して、
高いLTVの商品に資源を集中させましょう。
リピート率向上施策を実行する
リピート率を上げることが、
見込み利益アップの最短ルートなんです。
というのも、新規顧客を獲得するコストって
既存顧客にリピートしてもらうコストの5倍もかかるから。
具体的な施策としては、
- アフターフォローの充実
- 定期的なコミュニケーション
- 次回購入のタイミングでの声かけ
こんな感じですね。
例えばですが、
化粧品を売ってる会社だったら、
「そろそろなくなる頃ですよね」って
タイミングよくメッセージを送るんです。
そうすると、お客さんは
「あ、ちょうどなくなりそうだった」
って思って自然にリピート購入してくれる。
リピート率の計算方法も覚えておくといいですよ。
月間リピート顧客数を累計新規顧客数で割れば、
月間リピート率が出せます。
この数字を毎月チェックして、
下がってきたら改善策を打つ。
そうやって継続的にリピート率を上げていけば、
見込み利益はどんどん積み上がっていくんです。
顧客セグメント別に戦略を変える
お客さんを一括りにしちゃうのは、
めちゃくちゃもったいないことなんです。
なぜなら、お客さんのタイプによって
求めてるものが全然違うから。
例えば、
- 新規顧客:信頼関係の構築が最優先
- リピーター:満足度の維持と向上
- VIP顧客:特別感のある体験の提供
こんな風に分けられますよね。
新規のお客さんには、
まず「この会社から買って良かった」
って思ってもらうことが大切。
だから丁寧なサポートや
期待を上回るサービスを提供するんです。
一方で、何度も買ってくれるVIPのお客さんには、
限定商品の先行案内とか
特別割引とかで特別感を演出する。
セグメント分けの基準は、
購入回数、購入金額、最終購入日なんかで決められます。
それぞれのセグメントに合わせた
アプローチをすることで、
顧客満足度も売上も同時に上がるんです。
結果的に、各セグメントからの
見込み利益が最大化されるってわけです。
クロスセル・アップセルを強化する
既存のお客さんに追加で買ってもらうのが、
利益を伸ばす一番効率的な方法なんです。
だって、すでに信頼関係ができてるから
新規開拓するより圧倒的に楽だから。
クロスセルとアップセルの違いは、
- クロスセル:関連商品を提案する
- アップセル:より高価格帯の商品を提案する
この2つですね。
例えば、パソコンを買ったお客さんに
マウスやキーボードを提案するのがクロスセル。
同じお客さんに、より高性能な
上位モデルを提案するのがアップセルです。
タイミングも超重要で、
購入直後とか、使い始めて満足してる時が狙い目。
「せっかくだから一緒にいかがですか?」
みたいな自然な流れで提案するんです。
ここで大切なのは、
お客さんの利益を最優先に考えること。
無理やり売りつけるんじゃなくて、
「これがあるともっと便利になりますよ」
って感じで提案するんです。
そうすると、お客さんも喜んで追加購入してくれて、
あなたの見込み利益もグンと上がります。
顧客維持コストを最適化する
お客さんを維持するためのコストを
できるだけ抑えることも重要なんです。
なぜかというと、
維持コストが高すぎると利益が圧迫されちゃうから。
でも、コストを削りすぎて
サービス品質が下がるのもダメですよね。
最適化のポイントは、
- 自動化できる部分は自動化する
- 効果の薄い施策は見直す
- 顧客満足度を下げずにコストカット
こんな感じです。
例えば、定期的な顧客フォローを
全部手動でやってたとしますよね。
それをメール配信システムで自動化すれば、
人件費を大幅に削減できます。
でも、重要なお客さんには
個別対応を続けるとか、
メリハリをつけるのが大切。
また、効果測定も欠かせません。
維持コストに対して
どのくらいのリピート売上が生まれてるか、
常にチェックしておくんです。
費用対効果が悪い施策は思い切ってやめて、
効果の高い施策に集中する。
そうやってコストを最適化していけば、
同じ売上でも利益率がグッと上がって、
見込み利益の最大化につながるんです。
数値計測で失敗しないための4つの注意点
数値計測で失敗する人って、
実は共通する4つの落とし穴にハマってるんです。
この4つの注意点を知っておけば、
データに振り回されることなく正しい判断ができます。
その4つが、
- データの精度を定期的に検証すること
- 短期的な変動に惑わされないこと
- 業界平均と比較して判断すること
- 継続的な改善サイクルを回すこと
なんですよね。
どれも当たり前に見えるかもですが、
実際にできてる人は意外と少ない。
特に最初のうちは、
データの見方で迷っちゃうことが多いんです。
それぞれ詳しく解説していきます。
データの精度を定期的に検証すること
データの精度を定期的にチェックするのが、
計測で失敗しないための第一歩です。
なぜかっていうと、
間違ったデータで判断したら全部台無しになっちゃうから。
例えば、
- 計測ツールの設定ミス
- データの取得漏れ
- 重複カウントの発生
こんなことが起きがちなんです。
特にLTVを計算するときって、
商品ごとのデータが正確じゃないと意味がない。
売り切り商品とサブスク商品で
計算方法も違うわけですし。
データが間違ってたら、
「この商品めっちゃ儲かってる!」
って思い込んじゃうかもしれません。
でも実際は赤字だったりして。
だからこそ、月に1回は
データの精度をチェックする習慣をつけましょう。
計測ツールの数値と実際の売上を照らし合わせて、
ズレがないか確認するんです。
最初は面倒に感じるかもですが、
これをやっとくだけで判断ミスがグッと減ります。
短期的な変動に惑わされないこと
短期的な数字の上下に一喜一憂しちゃダメです。
どうしてかというと、
ビジネスの数字って日々バラつくのが普通だから。
具体例を挙げると、
- 今日だけリピート率が下がった
- 今週だけ売上が落ちた
- 今月だけLTVが低い
みたいな状況ですね。
こういう短期的な変動を見て、
「やばい!何か問題が起きてる!」
って慌てちゃう人が多いんです。
でも実際は、季節要因だったり
たまたまの偶然だったりすることがほとんど。
例えば、月間リピート率を計算するとき、
1日だけ見て判断しちゃダメなんです。
最低でも3ヶ月、
できれば半年くらいのデータを見て判断する。
そうすると本当のトレンドが見えてきます。
僕の知り合いも、
1週間だけ売上が下がって焦ってたんですが、
月全体で見たら過去最高だったなんてことがありました。
だからこそ、長期的な視点で
データを見る癖をつけましょう。
業界平均と比較して判断すること
自分のデータだけ見てても、
それが良いのか悪いのか分からないんです。
なんでかっていうと、
比較対象がないと判断基準がないから。
例えば、
- 自社のリピート率30%
- 業界平均のリピート率20%
- 競合他社のリピート率25%
こんな感じで比較すると分かりやすいですよね。
自分だけ見てたら、
「30%って低いのかな?」
って不安になっちゃうかもしれません。
でも業界平均より10%も高いなら、
むしろ優秀だってことが分かります。
商品ごとの見込み利益を計算するときも同じで、
業界の相場を知っておくと判断しやすい。
LTVも業界によって全然違うので、
自分の業界の平均値は調べておきましょう。
ただし、業界平均はあくまで参考程度に。
大切なのは、自分のビジネスが
継続的に成長してるかどうかです。
業界平均を下回ってても、
毎月改善してるなら問題ありません。
継続的な改善サイクルを回すこと
数値を計測するだけじゃ意味がなくて、
そのデータを使って改善し続けることが大切です。
理由は簡単で、
計測は改善のための手段だから。
改善のサイクルっていうのは、
- データを見る
- 問題点を見つける
- 改善策を考える
- 実行する
この流れを繰り返すことです。
例えば、リピート率が低いことが分かったら、
「なんで低いんだろう?」
って原因を考えるんです。
商品の品質に問題があるのか、
フォローアップが足りないのか、
価格設定が間違ってるのか。
原因が分かったら改善策を実行して、
また数値をチェックする。
僕が見てきた成功してる人って、
みんなこのサイクルを回してます。
逆に失敗する人は、
データを見るだけで満足しちゃう。
「今月のLTVは◯◯円でした」
で終わっちゃうんです。
でもそれじゃもったいない。
システム全体の見込み利益を上げるためにも、
必ず改善アクションまでセットで考えましょう。
システム全体のLTVを算出すべき4つの理由
システム全体のLTVを計算するのって、
実はビジネスを成功させる上で超重要なんです。
これをしっかり把握できれば、
あなたのビジネスが一気に安定して成長できるようになります。
その理由が、
- 長期的なビジネス戦略を立てられるから
- 顧客一人当たりの価値を明確にできるから
- マーケティング投資の判断基準になるから
- 事業の成長性を客観的に評価できるから
なんですよね。
多くの人がこのLTV計算を軽視してるんですが、
これができてないとビジネスが迷走しちゃう。
でも逆に言うと、
これさえ押さえとけば勝ち組になれるってことです。
詳しく見ていきましょう。
長期的なビジネス戦略を立てられるから
長期的なビジネス戦略を立てるには、
システム全体のLTVが絶対に必要になってきます。
だって、お客さん一人から
どれくらいの利益が見込めるかが分からないと、
将来の計画なんて立てられないじゃないですか。
例を挙げると、
- 1年後の売上予測
- 3年後の事業規模
- 投資すべき分野の判断
こういうのが全部見えてくるんです。
もっと具体的に言うなら、
メルマガ読者が1000人いて、
LTVが5万円だとしましょう。
そしたら、現在の読者だけでも
5000万円の売上が見込めるってことになります。
ここからが大切なんですけど、
この数字があるからこそ、
「来年は読者を2000人にしよう」
みたいな具体的な目標が立てられるんです。
逆にLTVが分からないと、
「なんとなく頑張ろう」
っていう曖昧な戦略しか立てられない。
だからこそ、
長期戦略にはLTVが欠かせないんです。
顧客一人当たりの価値を明確にできるから
顧客一人当たりの価値を数字で把握できるのが、
LTV算出の最大のメリットなんですよね。
これが分かると、
お客さんに対する接し方が根本的に変わってきます。
具体的には、
- どこまでサポートに時間をかけるべきか
- どれくらいの特典を付けるべきか
- リピート購入のためにどんな施策をするか
こんなことが全部判断できるようになります。
例えばですが、
LTVが10万円のお客さんなら、
1万円相当のサポートをしても全然ペイするじゃないですか。
でも、LTVが1万円のお客さんに
同じだけのサポートをしたら赤字になっちゃう。
そんなふうに、
お客さんごとの価値が見えてくると、
どこにどれだけのリソースを割くべきかが明確になるんです。
さらに言うと、
価値の高いお客さんを大切にして、
そういう人をもっと集めようって戦略も立てられます。
結果として、
効率的にビジネスを回せるようになるんです。
マーケティング投資の判断基準になるから
マーケティングにお金をかけるとき、
LTVがあると投資判断がめちゃくちゃ楽になります。
なぜなら、
「このお客さんから最終的にいくら利益が出るか」
が分かってるからです。
判断基準として使えるのは、
- 広告費をいくらまでかけていいか
- どの媒体に投資すべきか
- 新規獲得とリピート施策のバランス
こういった部分ですね。
例えば、LTVが3万円だとしたら、
新規のお客さんを獲得するのに
1万円までなら広告費をかけても利益が出ます。
逆に2万円かかる広告なら、
明らかに赤字になっちゃいますよね。
どうしたらいいかと言うと、
この基準があることで、
無駄な広告費を使わずに済むんです。
また、複数の広告媒体を試すときも、
LTVを基準にして効果を比較できます。
「Facebook広告は獲得単価8000円、
Google広告は12000円だから、
Facebookの方が良い」
みたいな判断ができるってことです。
結果的に、
マーケティングの精度が上がって利益も増えます。
事業の成長性を客観的に評価できるから
事業の成長性を測るのに、
LTVほど分かりやすい指標はないんです。
これがあることで、
感情じゃなくて数字でビジネスの状況が把握できます。
評価できる項目は、
- 月ごとのLTVの変化
- 競合他社との比較
- 改善施策の効果測定
こんな感じですね。
例えばなんですが、
3ヶ月前のLTVが2万円で、
今月が2万5000円だとしましょう。
そしたら、この3ヶ月で
お客さん一人当たりの価値が25%も上がったってことになります。
これって、明らかに事業が成長してる証拠じゃないですか。
さらに詳しく見ていくと、
「なぜLTVが上がったのか」
も分析できるようになります。
商品の質が良くなったのか、
アフターフォローが改善されたのか、
リピート率が上がったのか。
そういった要因を特定できれば、
さらに効果的な改善策を打てるようになるんです。
結局のところ、
LTVは事業の健康状態を示すバロメーターなんですよね。
総利益を正確に計算する5つのステップ
ビジネスで一番大切なのって、
実は総利益をきちんと把握することなんです。
この5つのステップをマスターすれば、
あなたのビジネスの本当の収益力が
手に取るように分かるようになります。
その5つのステップが、
- STEP1. 各商品の売上金額を整理する
- STEP2. 商品別の売上を合算する
- STEP3. 返品・キャンセル分を差し引く
- STEP4. 計算結果を検証する
- STEP5. 定期的に数値を更新する
なんですよね。
多くの人がなんとなくで
売上を把握してるんですが、
それじゃあビジネスは成長しません。
正確な数字を知ってこそ、
次の戦略が立てられるんです。
順番に詳しく説明していきますね。
STEP1. 各商品の売上金額を整理する
各商品の売上金額を整理するのは、
総利益計算の土台作りです。
なぜかっていうと、
商品ごとの数字が曖昧だと
全体の利益も曖昧になっちゃうから。
例えば、こんな風に整理するんです。
- 商品A:月50万円
- 商品B:月30万円
- 商品C:月20万円
みたいな感じですね。
ここで大事なのは、
商品ごとにきっちり分けること。
「だいたいこのくらい」じゃなくて、
正確な数字を出すのがポイントです。
売上管理システムを使ってる人なら
レポート機能で簡単に出せますし、
手動で管理してる人は
エクセルで表を作るといいでしょう。
でもね、ここで注意したいのが
売上のタイミングなんです。
決済が完了した日で計算するのか、
商品を発送した日で計算するのか、
そこを統一しておかないと
後でズレが生じちゃいます。
だからこそ、
各商品の売上を正確に整理することが
総利益計算の第一歩になるんです。
STEP2. 商品別の売上を合算する
商品別の売上を合算するっていうのは、
システム全体の売上を把握するためです。
というのも、
個別の商品売上だけ見てても
ビジネス全体の状況は見えないからなんです。
具体的には、
- 全商品の売上を足し算する
- 月単位や年単位で集計する
- カテゴリー別でも分けてみる
こんな作業をやっていきます。
さっきの例で言うなら、
商品A(50万)+商品B(30万)+商品C(20万)
=合計100万円って感じですね。
でも、ただ足し算するだけじゃ
もったいないんですよ。
どの商品が一番稼いでくれてるかとか、
どのカテゴリーが伸びてるかとか、
そういう分析も同時にやっちゃいましょう。
そうすると、
「商品Aに力を入れた方がいいな」とか
「商品Cはもう少し改善が必要だな」とか
次の戦略が見えてくるんです。
合算作業って地味に見えるけど、
実はビジネスの方向性を決める
めちゃくちゃ重要な作業なんです。
STEP3. 返品・キャンセル分を差し引く
返品・キャンセル分を差し引くのは、
実際の利益を正確に把握するためです。
なぜなら、
売上として計上したものでも
返品されちゃったら利益にならないからです。
例えば、こんなケースがありますよね。
- 商品の不具合による返品
- お客さんの都合でのキャンセル
- 決済エラーによる取り消し
こういうのを全部洗い出すんです。
月100万円の売上があったとしても、
返品が5万円分あったら
実際の売上は95万円になります。
たった5万円って思うかもしれないけど、
年間で考えると60万円の差になるんです。
これって結構大きいですよね。
だから返品・キャンセルの管理は
しっかりやっておいた方がいいんです。
返品率が高い商品があったら、
商品の品質を見直したり、
販売ページの説明を改善したり、
対策も打てるようになります。
正確な利益を知るためにも、
返品・キャンセル分の差し引きは
絶対に忘れちゃいけない作業です。
STEP4. 計算結果を検証する
計算結果を検証するっていうのは、
数字の間違いを防ぐためです。
どんなに慎重に計算しても、
人間だからミスは起こっちゃうものなんです。
検証の方法としては、
- 前月との比較をしてみる
- 別の方法で計算し直してみる
- 第三者にチェックしてもらう
こんな感じでやってみてください。
例えば、
先月が80万円だったのに
今月が200万円になってたら
「あれ?何かおかしいな」って気づけますよね。
急激な変化があった場合は、
その理由をちゃんと説明できるかどうか
確認してみるんです。
新商品をリリースしたとか、
大きなキャンペーンをやったとか、
そういう理由があれば納得できます。
でも特に理由が思い当たらない場合は、
計算ミスの可能性が高いです。
検証作業って面倒くさいけど、
間違った数字でビジネス判断しちゃったら
大変なことになっちゃいます。
だからこそ、
計算結果の検証は必ずやっておきましょう。
STEP5. 定期的に数値を更新する
定期的に数値を更新するのは、
ビジネスの現状を常に把握するためです。
なぜかというと、
古い数字でビジネス判断してたら
時代遅れの戦略になっちゃうからなんです。
更新のタイミングとしては、
- 毎週末に週次で更新
- 月末に月次で更新
- 四半期ごとに詳細分析
こんな感じがおすすめです。
僕の知り合いの経営者さんは、
毎週月曜日の朝一番に
前週の数字をチェックしてるそうです。
そうすることで、
「今週はもう少し頑張ろう」とか
「この調子でいけば目標達成できそう」とか
リアルタイムで判断できるんですって。
逆に、
月に一回しか数字を見ない人は
問題が起きても気づくのが遅くなっちゃいます。
売上が下がり始めてても、
1ヶ月後に気づいたんじゃ
対策が後手後手になっちゃうんです。
定期的な更新って習慣化するまでは
ちょっと大変かもしれないけど、
慣れちゃえば5分程度でできる作業です。
ビジネスを成長させるためにも、
数値の定期更新は欠かせない習慣なんです。
アクセス単価を活用した効果測定法3つ
アクセス単価って聞いたことありますか?
これ、WEBマーケティングで
めちゃくちゃ重要な指標なんです。
この3つの方法をマスターすれば、
広告の無駄遣いが一気になくなって、
利益を最大化できるようになります。
その3つの方法が、
- 広告費用対効果を数値化する
- ランディングページの改善点を見つける
- 最適な広告予算を設定する
なんですよね。
多くの人が感覚で広告を回してるけど、
それだと損してることが多いんです。
数字で管理することで、
確実に利益を上げられるようになります。
順番に詳しく説明していきますね。
広告費用対効果を数値化する
広告費用対効果の数値化は、
アクセス単価を使えば
めちゃくちゃカンタンにできます。
なぜかというと、
アクセス単価が分かれば
広告費と利益の関係が一発で見えるから。
具体的には、
- システム全体の利益を把握する
- ランディングページのアクセス数を調べる
- 利益をアクセス数で割る
この流れで計算するんです。
例えばですね、
システム全体で100万円の利益があって、
ランディングページに1万アクセスあったとします。
そうすると、
アクセス単価は100円になりますよね。
これが分かると、
「1アクセスあたり100円の価値がある」
って明確に判断できるんです。
だから広告費が1アクセス80円なら、
20円の利益が出るって分かる。
逆に1アクセス150円の広告なら、
50円の赤字になるって判断できます。
こんな風に数値化することで、
感覚じゃなくて確実な判断ができるんです。
ランディングページの改善点を見つける
ランディングページの改善点って、
アクセス単価の変化を見れば
すぐに分かっちゃうんです。
どういうことかって言うと、
アクセス単価が下がったら
ページに問題があるってことだから。
改善前後で比較するポイントは、
- 同じアクセス数での利益の変化
- コンバージョン率の推移
- 顧客単価の変動
こういった数字を見るんです。
たとえばね、
ページを変更する前は
アクセス単価が100円だったとします。
でも変更後に80円に下がったら、
明らかにページが悪くなってるってこと。
逆に120円に上がったら、
改善が成功してるって分かります。
このデータがあれば、
どの部分を直せばいいかも見えてくる。
例えば、アクセス数は同じなのに
利益が下がってたら、
コンバージョン率が悪くなってるんです。
そしたらボタンの色を変えたり、
キャッチコピーを見直したりすればいい。
アクセス単価を定期的にチェックすることで、
ページの健康状態が手に取るように分かります。
最適な広告予算を設定する
最適な広告予算の設定は、
アクセス単価を基準にすれば
絶対に失敗しないんです。
理由はシンプルで、
利益が出る範囲でしか
広告費を使わないようにできるから。
予算設定の基本ルールは、
- アクセス単価より安い広告を選ぶ
- 利益率を考慮した上限を決める
- 段階的に予算を増やしていく
この3つを守ることですね。
さっきの例で言うと、
アクセス単価が100円なら、
広告費は80円以下に抑える。
そうすれば1アクセスあたり
20円の利益が確実に出ますよね。
月に1万アクセス集めたら、
20万円の利益になる計算です。
でもここで注意したいのが、
いきなり大きな予算を使わないこと。
最初は小さく始めて、
利益が出ることを確認してから
徐々に予算を増やしていくんです。
例えば、最初は月10万円から始めて、
利益が出たら20万円、30万円と
段階的に増やしていく。
こうすることで、
リスクを最小限に抑えながら
利益を最大化できるようになります。
アクセス単価を基準にした予算設定は、
ビジネスを安定させる最強の方法なんです。
利益向上につながる実践テクニック6選
ビジネスの利益を上げるには、
実は6つのポイントを押さえるだけでOKなんです。
この6つを実践すれば、
今の売上を2倍、3倍にすることも夢じゃありません。
その6つのテクニックが、
- LTVの高い顧客層を特定する
- アクセス単価の低い集客チャネルを見直す
- 商品の価格設定を最適化する
- リピート購入率を向上させる
- 顧客獲得コストを削減する
- 売上データを可視化して共有する
なんですよね。
どれも難しそうに聞こえるかもですが、
実際はシンプルな方法ばかりです。
順番にやっていけば、
確実に利益アップにつながりますよ。
それぞれ解説していきます。
LTVの高い顧客層を特定する
LTVの高い顧客層を見つけることが、
利益向上の一番の近道なんです。
なぜかって言うと、
お金をたくさん使ってくれる人が分かれば、その人たちに集中できるから。
例えば、
- 月に3回以上買い物する人
- 高額商品を迷わず購入する人
- 長期間サービスを使い続ける人
こんな特徴を持つ人たちですね。
LTVっていうのは、
一人のお客さんが生涯で使ってくれるお金の合計のこと。
計算方法は簡単で、
システム全体の見込み利益をメルマガ読者数で割るだけです。
例えば、100万円の利益があって、
メルマガ読者が1000人いたら、LTVは1000円になります。
でもね、ここからが大切なんですけど、
全員が同じLTVじゃないんですよ。
中には5000円使ってくれる人もいれば、
100円しか使わない人もいる。
だから、高いLTVの人を見つけて、
その人たちの特徴を調べることが重要なんです。
そうすれば、同じような人を集めることで、
効率よく利益を上げられるようになります。
アクセス単価の低い集客チャネルを見直す
アクセス単価が低いチャネルを見つけることで、
広告費を大幅に削減できるんです。
どうしてかと言うと、
同じお客さんを集めるのに安い方法があるなら、そっちを使った方がお得だから。
具体的には、
- SNSからの自然流入
- 検索エンジンからのアクセス
- 口コミや紹介による集客
こういった方法ですね。
アクセス単価の計算って、
実はめちゃくちゃ簡単なんです。
システム全体の利益を
ランディングページのアクセス数で割るだけ。
例えば、50万円の利益があって、
1万アクセスあったら、アクセス単価は50円です。
でも、広告で1アクセス100円払ってたら、
明らかに損してることになりますよね。
そんな時は、
もっと安い集客方法を探すべきなんです。
例えば、YouTubeで情報発信したり、
ブログを書いて検索からアクセスを集めたり。
最初は時間がかかるかもですが、
長期的には広告費を大幅に削減できます。
だからこそ、
アクセス単価を常にチェックして、効率の良い集客方法を見つけましょう。
商品の価格設定を最適化する
商品の価格を適切に設定することで、
利益を最大化できるんですよね。
その理由は、
価格が高すぎても低すぎても、結果的に利益が減ってしまうから。
よくある失敗例として、
- 安すぎて利益が出ない
- 高すぎて誰も買わない
- 競合と同じ価格にしてしまう
こんなパターンがありますね。
価格設定で一番大切なのは、
お客さんが感じる価値と価格のバランスなんです。
例えば、1万円の商品でも、
お客さんが3万円の価値を感じてくれれば、喜んで買ってくれます。
逆に、1000円の商品でも、
500円の価値しか感じなければ、誰も買いません。
だから、まずはお客さんにとっての価値を
しっかりと伝えることが重要なんです。
そのためには、
商品の特徴じゃなくて、お客さんが得られるメリットを説明する。
「この商品を使えば、こんな良いことがありますよ」
って具体的に示してあげるんです。
価格設定は一度決めて終わりじゃなくて、
定期的に見直して最適化していくことが大切ですね。
リピート購入率を向上させる
リピート購入率を上げることが、
利益向上の最も確実な方法なんです。
なぜなら、
新しいお客さんを獲得するより、既存のお客さんにもう一度買ってもらう方が簡単だから。
リピート購入を促すには、
- 商品の品質を高く保つ
- アフターサービスを充実させる
- 定期的にお客さんとコミュニケーションを取る
こういったことが効果的ですね。
特に大切なのは、
お客さんとの関係を継続することなんです。
一度商品を売って終わりじゃなくて、
その後もメールやSNSでつながり続ける。
例えば、商品を購入してくれた人に、
「使ってみていかがですか?」ってメッセージを送ったり。
困ったことがあったら、
すぐにサポートしてあげたり。
そうやって信頼関係を築いていけば、
自然とリピート購入してくれるようになります。
また、リピート購入しやすい仕組みを作ることも重要で、
定期購入プランを用意したり、会員限定の特典を提供したりするんです。
お客さんにとって便利で、
お得感のある仕組みを作れば、リピート購入率は確実に上がりますよ。
顧客獲得コストを削減する
顧客獲得コストを下げることで、
利益率を大幅に改善できるんです。
理由はシンプルで、
お客さん一人を獲得するのにかかる費用が安くなれば、その分利益が増えるから。
コスト削減の方法として、
- 広告の効果測定を徹底する
- 成果の出ない広告を停止する
- 口コミや紹介制度を活用する
こんなアプローチがありますね。
広告って、実は無駄が多いんですよ。
例えば、Facebook広告で月10万円使ってるけど、
実際に売上につながってるのは3万円分だけ、みたいなことがよくあります。
そういう時は、効果の出てない7万円分を
他の方法に回した方が絶対良いんです。
具体的には、成果の出てる広告だけに予算を集中したり、
SNSでの情報発信に力を入れたりですね。
また、既存のお客さんに紹介してもらう仕組みも
めちゃくちゃ効果的なんです。
「お友達を紹介してくれたら、次回10%オフ」
みたいな特典を用意するだけで、紹介が増えます。
紹介で来たお客さんは、
最初から信頼度が高いので、購入率も高くなるんですよね。
だからこそ、
顧客獲得コストを常に意識して、効率的な集客方法を見つけることが重要です。
売上データを可視化して共有する
売上データを見える形にして共有することで、
チーム全体の利益意識が高まるんです。
その理由は、
数字が見えると、何をすべきかが明確になって、みんなが同じ方向を向けるから。
データ可視化のポイントは、
- 日々の売上をグラフで表示する
- 商品別の利益率を比較する
- 目標との差を分かりやすく示す
こういった工夫ですね。
例えば、今月の売上目標が100万円だとして、
現在70万円だったら、あと30万円必要ってすぐ分かります。
そうすると、「今週は頑張らないと」
って自然に思えるようになるんです。
また、どの商品が一番利益を生んでるかも
グラフで見ると一目瞭然になります。
利益率の高い商品が分かれば、
そこに集中して売上を伸ばせますよね。
データ共有で大切なのは、
難しい数字じゃなくて、誰でも理解できる形にすること。
売上の合計、今日の利益、目標まであといくら、
こんなシンプルな情報で十分なんです。
毎日チームで数字を確認する習慣を作れば、
自然と利益向上への意識が高まって、結果もついてきますよ。
利益計算で見落としがちな注意点4つ
利益計算って、
実は思ってる以上に落とし穴があるんです。
この4つのポイントを押さえとけば、
正確な利益が分かって経営判断が楽になります。
見落としがちな注意点は、
- 隠れたコストを見逃さないこと
- 計算期間を統一すること
- データの精度を定期的に確認すること
- 季節変動を考慮に入れること
なんですよね。
どれも地味だけど、
めちゃくちゃ大事なポイントです。
一つでも見落とすと、
利益計算が大きく狂っちゃうんです。
順番に詳しく説明していきますね。
隠れたコストを見逃さないこと
隠れたコストっていうのは、
パッと見では分からない費用のこと。
これを見落とすと、
実際の利益が全然違っちゃうんです。
例えば、
- サーバー代やツール代
- 外注費や人件費
- 決済手数料
こんな感じの費用ですね。
メルマガ配信システムの月額料金とか、
ランディングページのサーバー代とか、
意外と忘れがちなんですよ。
さらに言うと、
クレジットカード決済の手数料も
結構バカにならない金額になります。
でもって、こういう費用って
毎月かかってくるじゃないですか。
だから年間で計算すると、
思ってる以上に大きな金額になるんです。
例えば月3万円の経費でも、
年間だと36万円になりますからね。
だからこそ、
隠れたコストは必ずチェックしましょう。
計算期間を統一すること
計算期間を統一するっていうのは、
同じ期間で比較するってことです。
これができてないと、
正しい判断ができなくなっちゃいます。
具体的には、
- 月単位で統一する
- 年単位で統一する
- 四半期で統一する
みたいな感じですね。
よくあるのが、
広告費は月単位で見てるのに、
売上は年単位で見ちゃうパターン。
これだと比較にならないんですよ。
例えばですけど、
月の広告費が10万円で
年間売上が500万円だったとします。
一見すると利益率が良さそうに見えるけど、
実際は年間広告費が120万円かかってるわけです。
そうすると利益率が
全然違って見えてきますよね。
だからこそ、
期間は必ず統一して計算しましょう。
データの精度を定期的に確認すること
データの精度を確認するっていうのは、
数字が正しいかどうかをチェックすること。
間違ったデータで計算しても、
意味がないですからね。
チェックすべきポイントは、
- アクセス数の計測
- 売上データの記録
- 経費の漏れ
こんな感じです。
アクセス解析ツールって、
たまに数字がおかしくなることがあるんです。
設定ミスとか、
システムの不具合とかで
正確に計測できてない場合があります。
それから売上データも要注意ですね。
決済システムと
実際の入金額が違ってたり、
返金処理が反映されてなかったり。
こういうのって、
気づかないうちに積み重なって
大きな誤差になっちゃうんです。
だから月に一回は
データの精度をチェックしましょう。
季節変動を考慮に入れること
季節変動を考慮するっていうのは、
時期によって売上が変わることを計算に入れること。
これを無視すると、
将来の予測が全然当たらなくなります。
変動しやすいタイミングは、
- 年末年始
- ゴールデンウィーク
- お盆休み
こういう時期ですね。
年末年始って、
みんなお金を使いたがる時期じゃないですか。
だから普段より売上が上がりやすいんです。
逆にゴールデンウィークとかお盆は、
みんな旅行に行っちゃうから
売上が下がりがちなんですよね。
例えばですが、
12月の売上が100万円だったからって、
毎月100万円稼げるとは限らないんです。
12月は特別な月だから、
平均すると月80万円くらいかもしれません。
だからこそ、
季節変動も必ず考慮に入れて
利益計算をしていきましょう。
この記事の重要ポイントを整理
この記事の重要点をチェックリストにまとめました。
要点の最終確認
- 仮説検証分析は感覚ではなく数値で判断するビジネス改善法
- 現状データ収集→改善点特定→仮説立て→実行→検証の5ステップが基本
- LTVは顧客一人から生涯で得られる利益の総額
- 商品タイプ別にLTV計算方法が異なる(売り切り・サブスク)
- リピート率は月間リピート顧客数÷累計新規顧客数で算出
- 見込み利益最大化にはLTV高商品への集中投資が効果的
- アクセス単価はシステム全体利益÷アクセス数で計算
- データの精度確保と継続的な改善サイクルが成功の鍵
- 短期変動に惑わされず長期視点でデータを分析する
- 複数指標を組み合わせた総合的な判断が重要
まとめ
仮説検証分析を使った
ビジネス改善について
詳しく解説してきました。
数字を使った分析って
難しそうに感じるかもしれませんが、
実はとてもシンプルなんです。
大切なのは、
感覚ではなく数値で判断すること。
そして継続的に改善を続けることです。
LTVを正確に計算して、
リピート率を効果的に測定し、
見込み利益を最大化する。
この流れができるようになれば、
あなたのビジネスは
確実に成長していきます。
最初は小さな改善からでも構いません。
今日から一つずつ実践して、
数字の変化を確認してみてください。
データに基づいた判断ができれば、
無駄な時間やお金を使わずに済みます。
そして効果的な施策だけに
集中できるようになるんです。
ビジネスを本気で成長させたいなら、
今すぐ仮説検証分析を始めましょう。
あなたの売上が劇的に変わる
きっかけになるはずです。
よくある質問
仮説検証分析って何ですか?初心者でも分かるように教えてください。
仮説検証分析とは、あなたの予想を数字で確かめる方法です。「こうすれば売上が上がるはず」という予想を立てて、実際にやってみて、本当に効果があったかを数字でチェックします。感覚ではなく、しっかりとしたデータで判断できるようになるので、ビジネスの成功率がグンと上がるんです。
LTVの計算方法が分からないのですが、どうやって計算すればいいですか?
LTVの計算は商品タイプによって変わります。売り切り商品なら「商品価格×リピート回数」、サブスク商品なら「月額料金×継続月数」で計算できます。例えば月額5000円のサービスを平均6ヶ月使ってもらえるなら、LTVは3万円になります。まずは過去3ヶ月のデータを使って計算してみましょう。
リピート率が低くて困っています。どうすれば上げられますか?
リピート率を上げるには、お客さんとの関係を続けることが一番大切です。商品を売って終わりではなく、「使ってみていかがですか?」とメールでフォローしたり、困った時にすぐサポートしてあげたりしましょう。また、次回購入のタイミングで「そろそろなくなる頃ですよね」と声をかけると、自然にリピート購入してもらえます。
データを見ても何を改善すべきか分からないのですが、どこから手をつければいいですか?
まずは一番数字が悪い部分から改善しましょう。例えば、100人がサイトに来て3人しか買わないなら、97人がなぜ買わなかったのかを調べます。価格を見て帰ったのか、商品説明が分からなかったのか。一番大きな問題を見つけて、そこから一つずつ改善していけば、必ず結果は良くなります。
短期間で結果を出したいのですが、どのくらいの期間を見ておけばいいですか?
仮説検証分析は最低でも1ヶ月、できれば3ヶ月は様子を見ましょう。お客さんが商品を知ってから買うまでに時間がかかることもありますし、1週間だけでは正確な判断ができません。焦る気持ちは分かりますが、しっかりとデータが集まってから判断することで、本当に効果のある改善策が見つかります。
数字が苦手なのですが、それでも仮説検証分析はできますか?
もちろんできます!難しい計算は必要ありません。「今月は先月より売上が上がったか下がったか」「お客さんからの問い合わせは増えたか減ったか」といった簡単な比較から始めましょう。慣れてきたら少しずつ詳しい数字も見るようになれば大丈夫です。数字は苦手でも、継続して見ることで必ず分かるようになります。
【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ
こんにちは、なおとです。
ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。
なおとって誰やねんってなるかもしれないので
簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。
AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して
社畜辞めました。
特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、
なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。
正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。
「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。
僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を
稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。
「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を
期間限定で無料参加できます。
僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。
あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。
賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。